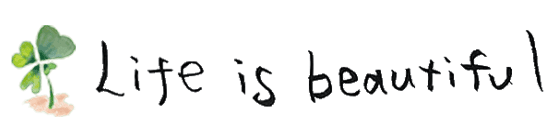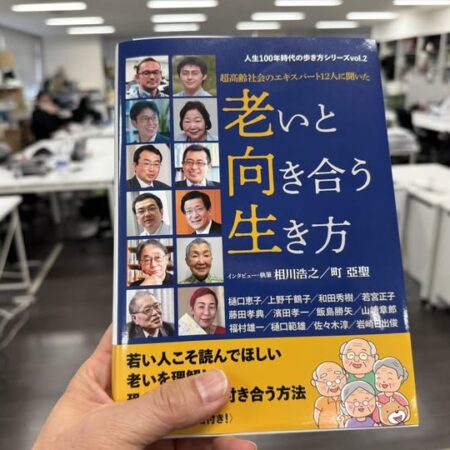ここは認知症の人たちを地域から隔離し、閉じ込めておくための「テーマパーク」なのではないか。
佐々木理事 2022年9月10日 Facebook記事より
認知症の人たちを集め、そこに「街」のような介護施設をつくり、その「街」の中で認知症の人たちが最期まで暮らす。
伝統的な街並み、都会的な街並み、そしてかつての植民地(インドネシア)を思わせる街並み・・・その人にとって、もっとも違和感のない「街」を選び、そこに自分の「家」を持ち、そこでくらしが完結する。
2008年の開設以来、認知症の人たちのユートピアとして注目されてきた「ホフウェイ(The Hogeweyk)」。

噴水のある広場、劇場、カフェやレストラン、美容室・・・街並みは美しく作り込まれ、居室も各個人のライフスタイルに合わせてコーディネートできる。確かに快適そうだが、一つしかない出入口は、外から入ることはできても、中から出ていくことはできない。
ここは認知症の人たちの「快適な隔離施設」なのではないか。
少し批判的なスタンスで、僕はこのホフウェイの見学に臨んだ。
結論から言えば、この先入観は少し修正が必要だった。
■施設の概要
ここにはもともと旧来型の高齢者施設が立地していた。
しかし「統合型ケア」のコンセプトを実現するため、2008年に現在の施設(ホフウェイ)に建て替えられた。
ホフウェイには、7人が暮らす「家」が27軒ある。
そして、いくつかの家が集簇して、それぞれ異なるテイストの3つのブロックを形成、それらが噴水のある広場につながり、広場の周りには劇場や管理棟、商業棟(カフェやレストラン、スーパーなどが入居)が配置されている。
広場も建物も道路もきれいに作り込まれていて、普通にオランダの街を歩いているような感覚になる。
■施設の位置づけ
ここに入居できるのは、重度の認知症と診断をされた人だけ。
地域の医療機関等で診断を受けた後、入居待機リストに名を連ね、順番が来るとSocial Coach(相談員)が自宅を訪問、手続きを行う。
重度認知症であるなどの資格要件を満たせば、経済的状況によらず誰でも入居ができる。日本の特別養護老人ホーム(要介護3以上で認知症があることが資格要件)に近い。入居者は近隣住民が多いが、家族が近隣に暮らしているという理由で、遠方から入居される方もいる。
入居者と家族の日常的な交流が大切にされており、本人の自宅の近くというよりも家族が面会しやすいことをより重視しているとのこと。
■施設のコンセプト
ここは施設ではなく街であり家である。
そんな考えから、まずはセントラルキッチンで調理をして、画一的な食事を提供することはやめた。
それぞれの家に「完璧なキッチン」を備え付け、入居者同士で食べたいものを一緒に考え、食事をスタッフとともに準備し、一緒に食べて、一緒に片づける。
また、今日は一人で食べたいものを食べよう。そんなこともできる。好きなものを買ってきて、自分で調理したり、調理を手伝ってもらったり。友人や家族と家で食べても、カフェやレストランで食べることもできる。庭のベンチでワインを飲みながらサンドイッチを楽しむこともできる。
倉庫も廃止して、そこをスーパーマーケットにした。つまり、倉庫の格納棚をスーパーの商品棚に変えたのだ。
入居者はここで食品や総菜、ジュースやワイン、そして文具や雑貨、衛生材料まで購入することができる。
必要なものを自分で買って、自宅に持ち帰り、自分で使う。
それぞれできる範囲で主体的に、時に支援を受けながらも「生活」する。
これは効果的なリハビリでもあるはず。
街路には段差もある。凹凸のあるタイルも使用されている。
広場には噴水がある。水深は60cmくらい。転落して溺れたらどうする?日本の介護施設なら絶対にそんな議論が起こりそうだ。
しかし、認知症だからといって噴水に飛び込む人はいない。
専門家の意見も参考にしながら、ゼロリスクよりも、普通の街に近づけることを選択した。
■ケアのコンセプト
「長く生きる」(生存期間)よりも「よりよく生きる」(QOL)がより大切である、ということが何度も強調された。
重度認知症であるということは、人生の最終段階に近いということ。全身状態の変化も、多くは自然なプロセスとして受容される。
人生の最終段階で点滴や経管栄養をすることはなく、病院に入院する人もいない。看取り率はほぼ100%。
食べる機能も徐々に落ちてくる。摂食嚥下障害の場合、その原因を診療看護師および医師がアセスメントし、改善が可能であれば改善する。食べる能力に応じてペースト食を準備することもあるし、食具が使えない人にはフィンガーフードを準備することもある。ただ、食べる意欲の低下、全身機能の低下に対しては、苦痛の緩和を最優先する。認知症の人の多くは苦痛を上手に訴えることができない。緩和医療の専門家とともに苦痛のアセスメントをするとともに、最期まで快適に過ごせるよう支援する。経口摂取が止まると、多くは2~3日で旅立っていく。
コロナ禍における対応も、なにがその人にとっての「よりよく生きる」ことなのかを優先して判断する。
具体的には、面会制限は行っていない。また施設内でのマスク着用の義務もない。感染を恐れ、家族面会を制限することで棄損される価値と、感染して死亡するかもしれないリスクと、どちらを取るのか。家族面会を制限し続ければ、結局、それはその人の生きる力にも悪影響を及ぼす。だからこそ、家族等やボランティアとの交流はコロナ前と同じように行っているという。実際に施設内で、コロナで亡くなった方もおられる。ただ、もちろん削減できるリスクは削減する。訪問時、ホフウェイでは、ちょうど入居者と介護専門職に対する4回目のワクチン接種が開始されたところだった。また、感染者が出れば、その家は一時的に隔離され、ケアスタッフはPPEを装着し支援にあたる。
その人が「よりよく生きる」ために必要なものは何なのか。
それは人によって異なる。だからこそ、介護・看護専門職は、入居時の面談(特に丁寧に行っている)に加え、日々の関わりの中で、その人の真のニーズをキャッチできることが非常に重要にある。
また、その人ができるだけ自分の力で生活ができるように「環境」を整える。環境とは、その人の身体機能に応じた生活空間のことだけではない。人と人とのかかわり、同じ「家」で暮らす他の入居者、家族、友人、職員、ボランティア、そしてその他の重要な人たち。このつながりを強めていくこと、再構築していくこと、それがケアを提供していく上でもっとも重要であると強調された。
しかし、実際には、施設に閉じ込めているではないか。
いや、そうではない。
この施設は、確かに中から外に向けては常時開かれてはいない。少なくとも一人で無許可に外出はできないようになっている。
しかし、外から中に向けては常に開かれている。
家族や友人はいつでも訪問できる。100人を超えるボランティアが常時出入りする。地域の人がスーパーやレストラン(いずれも年中無休)を利用する。
そして、ホフウェイ内部ではさまざまなイベントが開催され、外部から人が意図的に集める仕組みもある。地元の小学生も週に1度、施設内で活動する。
認知症の人たちは、ここから一人で外に出ていかなくても、いわば「娑婆の空気」をこの中で味わえる。
通常、高齢者施設ではさまざまなものが管理される。
しかし、ここはあくまで「家」であり「街」である。施設独自の特別な制約はない。
食べたいものを食べる。ワインを飲んで、たばこを味わう。楽しみを見つける。それを共有できる友達を作る。会いたい人と会う。そして週末は自宅に戻ることもできるし、アムステルダムの街でカフェや演劇を楽しむこともできる。リスクや医療を理由に、これらを一方的に禁止することは「人権の侵害」。大切なのは、リスクを減らすことではなく、リスクの対価を理解した上で、自分で選択できるよう支援することだという。
もちろん、これらの活動は一人ではできない。
しかし、日常生活はケアスタッフと生活支援スタッフ(Home Companion)が、趣味の活動や外出の支援は、ボランティアスタッフが1 on 1で対応してくれる。
■医療・ケアの提供体制
7人の認知症の人が暮らす「家」には、日中、ケアスタッフが1名、生活支援スタッフが半日滞在し、支援を行う。
食事は全員で食卓を囲むし、約半数は身体機能が保たれている(車椅子が必要ないレベル)ので、一人ひとりを個別に丁寧にケアする、という感じではない。一つの家族の生活をそっと見守り、そっとサポートするというイメージだ。
夜間は「家」にスタッフは常駐しない。巡回もない。ただし、居室や廊下にはモーションセンサーが設置されており、異状を察知すると施設内で待機しているスタッフが対応する。1人が受付に常駐(センサーのモニタリング)、6人が施設内に待機、必要時に対応する。
施設には24時間、診療看護師が配置され、主に医療的ケアや医療的アセスメント、そして介護職の支援を行う。
医師の定期的な訪問診療もある。
これはGP(家庭医)ではなく、医療は同じ組織内で雇用している老年病専門医。他に理学療法士・作業療法士などのサービスもあり(施設内にはリハビリサービスセンターも)健康管理を支援する。
急変時は診療看護師が対応、医師と連携しながら必要な支援を行う。
基本的には医療は施設内完結。
病院を受診することは、転倒・骨折などの事故を除くとあまりない。
■ボランティアの関わり
ボランティアは現在100名程度。もともと120人くらいいたが、コロナで減少してしまったとのこと。
ボランティアの多くも高齢者。独居の人も多い。特に入居者の遺族がボランティアとして関わりを続けてくれることもあるという。これはグリーフケアとしての側面もあるかもしれない。また、特に高齢・独居のボランティアにとっては、ここで誰かのために働く、というよりは、ここで働くことで自分の居場所や役割を見出しているのかもしれない。
結論から言えば、ここは「外に対して開かれたコミュニティ」。
中の街と外の街、人の流れはつながっている。
入居者の一人での外出は制限されているが、それでも、希望すれば自宅に帰ることも、近隣の街に出かけていけるようサポートする仕組みもある。
在宅療養していても一人での外出ができない。日常生活の範囲が自宅とデイサービスの行き来だけ、自宅への来訪者は医療介護の専門職だけ、そんな高齢者は少なくない。一人での外出に制限がある、という点では、在宅療養と比較しても実はそんなに大きな差はないのかもしれない。
一方、ホフウェイでは、自宅で療養生活よりも、より多くの社会との接点が生まれている可能性もある。家族も介護負担に疲弊することなく、家族間のより良好な関係を維持できている可能性もある。また7人という小さなユニットでの共同生活は、認知症高齢者の生活力を引き出し、一人あたりより少ない介護力で療養支援できている可能性もある。
自由に外に出られない、ということに対する抵抗感が完全に消えたわけではないが、それでも、施設を基点とした統合型ケアの1つの形であることは間違いない。
見学を終えて再び広場に戻ると、ピンクのカーディガンを羽織ったかわいい女性(推定年齢80代)が、ベンチでタバコを燻らせながら、僕らに笑顔で手を振ってくれた。その向いのカフェのテラスでは、同世代と思われる2人の男性が赤ワインのグラスを並べ、ボードゲームをしている。 住み慣れた自宅ではない。だけど、人生の最期の2年半を過ごす場所として、悪くはないのかもしれない。彼らの姿をみて、そんなことを思った。