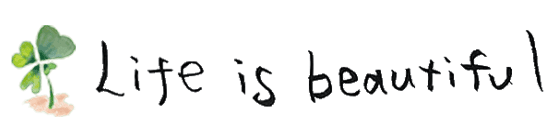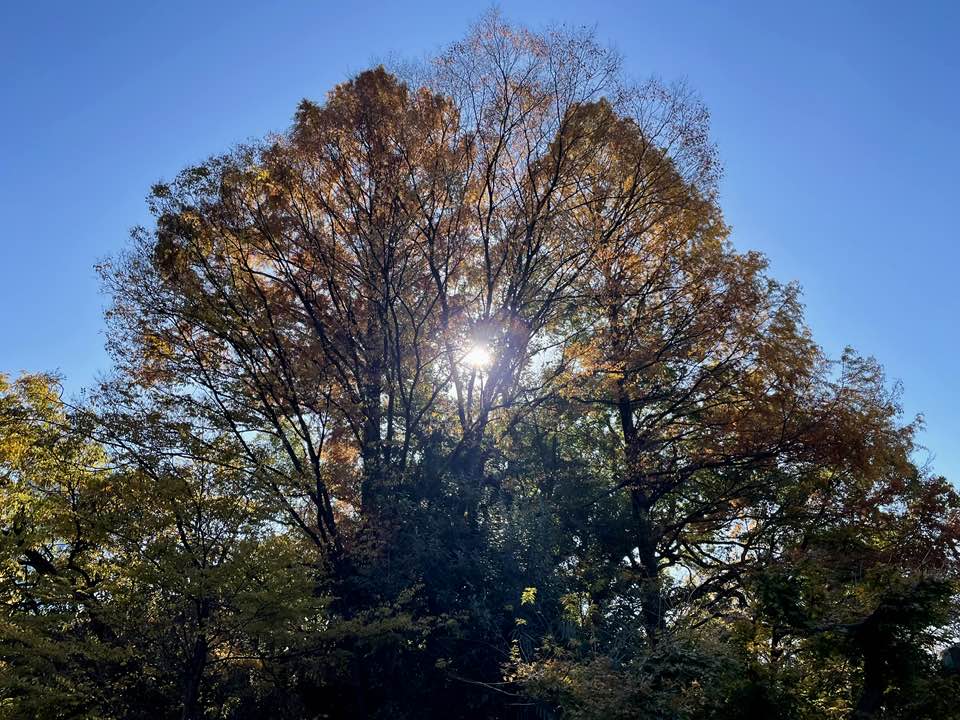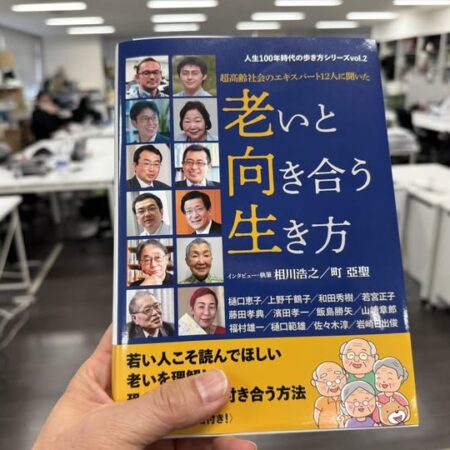もう少し根っこからきちんと議論する場が必要なのでは
いままさに診療報酬改定に向けて議論が行われています。
今回は「開業医から病院へ」という流れになりそうです。その方向性に異論はありませんが、国民が問題視している若い世代の社会保険料負担、その要因となっている後期高齢者医療費の大部分を占めるのは、実は入院医療費です。
国民の納得と病院経営の本当の意味での救済のためには、病床機能の抜本的な見直しと病床数の適正化・診療能力の集約化、効果的な医療への適切なインセンティブ設計が並行して行われる必要があると思います。
●病床数の削減
病院の赤字の主たる要因は病床稼働率の低下。
一般病床と療養病床は3割が空床、精神病床も約2割が空床です。
この「慢性不稼働病床」を放棄するだけで、その施設基準を満たすための設備や人材の負担を軽減できます。空床を減らすことで病床稼働率が上がれば収支は改善するはずです。
自公維が合意した11万床の病床削減は見送られる可能性が高そうですが、40万床が常時空床なのですから、この程度は削減しても現在の診療体制には影響を及ぼさないはずです。
医療技術の進歩によって抗癌剤の多くは入院が必要なくなったし、外科領域でも縮小手術が進化しています。カテーテルや内視鏡で治療完結できる病気も増えてきました。
下がり続ける入院依存率に応じてベッドを減らしていくのは合理的な判断であるはずです。
●病床機能の集約化
日本には小さな急性期病院・小さな総合病院がたくさんあります。
もちろん周辺30分に他に病院がない地域においては、最後の砦として病院を死守しなければなりません。
しかし都市部においてはどうでしょうか。
例えば小さな総合病院が5つある地域。
すべての病院が脳神経外科を標榜としていますが、しかし24時間対応で脳出血に対応できる病院は1つもありません。救急車で隣町まで搬送するしかありません。
5人の脳神経外科医が5つの総合病院で分散勤務するより、1か所に集まったほうが医療対応能力は強化されるはずです。脳外科医が1人だと重度疾患への対応は制限されます。一人で当直やオンコールを担当し続けるのも無理があります。しかし5人が集まれば、より高侵襲な手術にも対応できるし、当直体制の持続可能性も高まります。近くに脳外科がないことを心配される方もいるかもしれませんが、結局、命にかかわる事態においては救急車で大きな病院に行くしかない。これは専門医にとっても地域住民にとっても最適な状況でないように思います。
それぞれの地域の医療ニーズの充足状況を丁寧に見ながら、医療機能の集約化を進めていくことで、医療の質、経営の質の両面を改善することができるのではないでしょうか。
●「腕の良さ」に対するインセンティブ
ある病院で。
金曜日には退院できる状態の患者さん。もちろん帰してあげればいいのですが、主治医が提案したのは、月曜日にもう一度採血をやって結果を確認してから退院しましょう、というもの。患者さんは「丁寧に診てもらえてありがたい」と感じたかもしれませんが、実はこれは病院の経営会議の方針を受けての対応でした。金曜日に退院させると土日が空床になってしまう。しかし退院を月曜日まで延ばすことで、3日間分の診療報酬が余分に病院に入るのです。
日本の入院医療にはDPC(Diagnosis Procedure Combination:診断群分類包括評価)が導入されています。入院初期から後期にかけて入院の1日単価が3段階で下がるように設計されているので、早期退院を促す仕組みになってはいますが、短すぎる入院よりもある程度の日数までは入院させておいた方が病院収入は高くなります。制度設計上の「出来高+包括」折衷型の報酬体系がその行動インセンティブを生んでいます。
DPCでは患者を病名・手術・処置などの組み合わせで分類し、入院1日あたりの包括点数(定額)を設定します。報酬はおおむね次のような三段階構造です。
◆入院初期(急性期):1日あたりの点数が高い
◆中期:点数がやや下がる
◆後期(長期入院):点数がさらに下がる(逓減)
このように「1日単価は逓減」していく一方で、入院期間が一定日数(いわゆる“基準日数”)までは出来高部分や加算の影響で総額が増える設計になっています。そのため、病院にとっては「早すぎる退院」は必ずしも収益的に有利ではないのです。
たとえばDPCコード別に「包括支払いの対象日数(基準日数)」が設定されています。
多くのDPC群では、7〜14日あたりが「高単価期間」。それを超えると1日単価が逓減し最終的には出来高払いへ切り替わるケースもあります。つまり、たとえば10日で退院させるよりは14日で退院させたほうが病院の収益は大きくなる。過剰入院というのは言い過ぎですが、少なくとも早期退院促進」の強いインセンティブにはなりません。
行動の中立性を損ねる(患者利益よりも経営面の都合が優先される)ような制度設計は避けるべきです。
例えばDPCにおいては、急性期の検査・処置を前倒しすることで「包括部分の単価を稼ぐ」という報酬インセンティブが大きい一方で、早期退院支援に伴う報酬が少なく、バランスが悪くなっています。
DPC包括率の見直し、基準日数を短縮・早期退院でも減収にならない設計が必要だと思います。
また現状、特に高齢者は衰弱した状態で退院されることが少なくありません。入院前後での状態の変化が大きいと、家族の不安や介護負担も大きく、退院直後の再入院や死亡のリスクも高くなります。入院関連機能障害の多くは、せん妄(環境変化のストレス)、入院中のベッド上安静や禁食・栄養不足などが原因で生じます。
「入院中に事故を起こさなければいい、死ななければいい」ではなく、退院後の生活を見据えた治療計画をより高く評価する、すなわち退院支援・退院後の再入院率や死亡率も含めたバンドルペイメントなどを検討してもよいのではないでしょうか。
もう一つ、並行して進めるべきは在宅・施設ケア体制の強化です。
高齢者医療費の多くが入院医療費と述べましたが、現在、一般急性期入院の2/3は75歳以上の高齢者、1/3は85歳以上の高齢者が占めています。
そして85歳以上の高齢者はいわゆる「医療密度」が低いことがわかっています。
特に加齢に伴って増加するのは動脈硬化性疾患とがんですが、これらの精査加療はもちろん入院で行うべきです。高度な医療設備や高侵襲な治療が必要になるからです。
しかし、85歳以上でこれらの疾患で入院するケースは実は多くはありません。そのかなりの部分は肺炎や尿路感染などの感染症、そして転倒・骨折や心不全です。そしてこれらの疾患の多くは入院でなくても治療・管理ができなくはありません。
実は日本以外の国では「在宅入院」という選択肢があることが一般的です。
欧米豪では普通に行われていますし、お隣の台湾でも昨年から本格的にスタートしています。その結果、たとえば肺炎治療においては、死亡率・再入院率で病院入院と遜色なく、入院コストは1/3、治療日数は2/3、患者・家族満足度は100%であったと報告されています。
実は私たちはインドで民間保険会社と提携し、一部疾患群に対して在宅入院サービスを提供していますが、約8割の方が在宅で治療を完結できています。
在宅での急性期治療は、その環境が整えば別に難しいことではないのです。
そして、在宅や施設でのケア体制を制度面・人材面からしっかりと強化してくれれば、入院への依存をさらに下げることができます。
いまは入院できたら安心!と思っている高齢者の方やそのご家族も多いと思いますが、入院には副作用もあります(高齢者は10日間の入院で7年分の老化に相当する骨格筋量の減少、当院の患者さんにおいては死亡退院23%、自宅に戻れない人33%)。
入院でしかできないこと、自宅でもできること、そしてそれぞれのリスクと利益、しっかり考えてもらえれば、自宅での治療を選択したいという方も少なくないはずです。
85歳以上の高齢者の医療密度の低さにはもう1つの要因があります。
それは社会的入院。
自宅でみるのが大変だから入院してもらう、というもの。
介護保険サービスと違って医療保険には高額療養費による負担上限があるので、入院が長期化しても経済的負担が少ないというバグもあり、ある研究によれば、総医療費の最大約10%が社会的入院によるものではないかという指摘もあります。
これらは本来は入院ではなく、ケアとして評価されるべきもの。そしてその財源も人材も本来であれば介護保険制度でカバーされるべきものだと思います。
また例によって長くなってしまいましたが、
社会保障費を削減(または伸びを抑制)しつつ、医療の質と経営の質を改善するためには、
① 地域医療(特に要介護高齢者に対する在宅医療)と入院医療の役割分担
② 医療技術の進化、人口減少、ケアニーズの入院外シフトを考慮した病床数の見直し
③ 医療機能の集約化
④ そのための医療資源(財源・人材)の再分配
⑤ 合理的・効果的な医療に対するインセンティブ設計
これを進めていくしかないと思うのです。
また高度急性期・ICUについては、診療報酬で完結させるのではなく、地域の危機管理の観点から、診療報酬外の予算を確保してもよいのではないかと思います。
音喜多さんは頻回外来受診をやり玉に挙げておられます。もちろんここは改善したほうがよいとも思いますが、医療経済上のインパクトは入院適正化に比べると小さいと思います。
もちろん上記をきちんと機能させるためには、地域(外来・在宅・介護)をきちんと機能させる、そのための改革が並行して行らわれることが前提です。
また病床機能の適正化においては、もちろん適正な診療報酬上の評価も必要です。
日本はベッド数が多すぎるので、入院医療費も希釈されていますが、病床の果たしている機能(医療密度)に応じてより弾力的な診療報酬の設定が必要だと思います。
病床を減らした分だけ医療密度が濃くなり、より高度な医療が提供できるようになる。
専門職の密度が高くなり、対応力が強化され、余裕のあるシフトが組めて離職も少ない。
患者はより短期間で退院できて、最適な病診・医療介護連携で退院後の再入院率も少なく、結果として1日あたりの診療収入が増え、総診療収入も増える。
十分な経常利益も確保できて、地域や未来への継続的な投資もできる。
少なくとも急性期病院はこうあるべきではないでしょうか。
回復期(包括期)や療養病床についても思うところはたくさんありますが、診療報酬の議論は、小手先の上げる下げるではなく、医療に対する「ニーズ」の定量化をきちんと行うことから始めるべきではないかと思います。
昨日は、慶応義塾大学の井手先生にお声がけいただき、総務省・地方行財政ビジョン研究会で講演の機会をいただきました。
日本の在宅医療の現場から、そして世界の医療やケアの現場を実際に見てきた経験も踏まえて、日本の地域医療のあるべき姿と自治体に求められる役割についてお話をさせていただきました。
中医協の議論はみていてもどかしいところがたくさんあります。
厚労省の委員会や規制改革推進会議でも、各職能団体の方々の発言を聞いていると、目先の診療収入を守ることにやっきになっている印象を受けます。10年後、20年後は全然違う世界になっているはずなのに。
もう少し根っこからきちんと議論する場が必要なのではないかと思います。
そういう意味では、維新の「事業仕分け」的な医療改革案より、自民のゲノムやDxを中核に据えた医療改革案は実はかなり先進的だと思うのですが、ここにTechnology Orientedではなく、患者中心の合理的な肉付けが進むことを願います。
そして、なにより、何のために医療が存在しているのか、その根本を見失ってはいけないと思います。
好きで病気になる人はいません。そしてどんなに健康に気遣っても年を取れば必ず病気や障害が出てきます。
特に高額療養費など、当事者の立場で考えることを忘れないでほしいと思います。