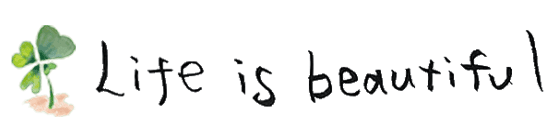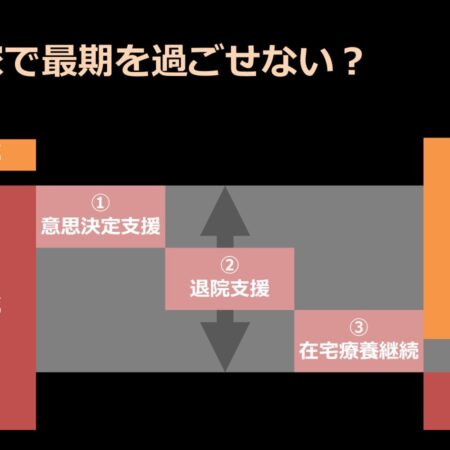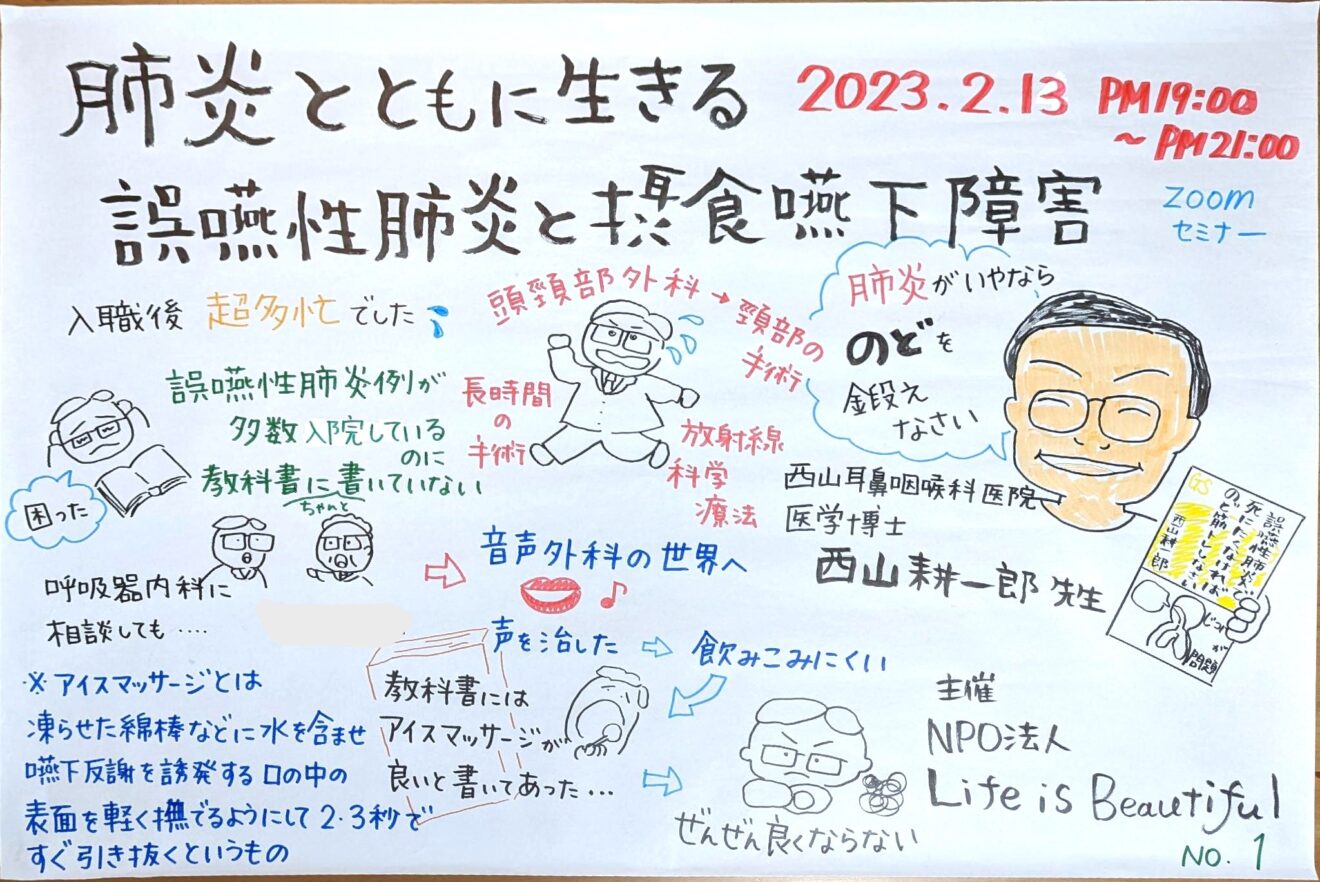いるべき場所に、いられること
「帰る―! 帰る-!」
80代の女性が髪を振り乱して、悲壮な表情で自動ドアの前に座り込んでいた。
困惑した表情の施設の介護スタッフは彼女をなだめすかし、手を引きながら、なんとかリビングスペースに戻しテーブルに着席させた。お茶を出して、もうすぐご家族が迎えに来ますからね、それまでここで一緒に待ちましょう、そんなスタッフの提案に一時的には同意した彼女だが、5分もしないうちに再び椅子から立ち上がり、手すりを伝いながら廊下を歩き始めた。
彼女は重度のアルツハイマー型認知症と診断されていた。
夫に先立たれ、一戸建てで一人暮らしをしていたが、生活力の低下を心配した家族の意向によって有料老人ホームに入居することになったのだ。彼女は施設に転居することを事前に説明されることなく、離れて暮らす子供の家に遊びにいくつもりで自宅を出発、そのままここに連れてこられていた。
それから彼女は毎日、施設の中を歩きまわり、出口を探した。
なぜ突然こんなところに閉じ込められたのか。家に帰らなければならない、家に帰してほしい。彼女にとっては当然の要求だ。しかし、施設の介護スタッフにとっては目が離せない、介護を拒否する、手のかかる認知症の入居者。最初のうちは「帰りたい」という彼女の切実な想いに共感を示していたスタッフも、徐々に対応が機械的になっていった。
家族が迎えに来てくれるはず。それが彼女の唯一の希望だった。
1日に何度も家族に電話し、迎えはいつになるのか問い続けた。家族は彼女との会話を苦痛に感じるようになり着信を拒否するようになった。彼女の孤独と不安、そして怒りはますます強くなっていった。そしてある日、トイレに誘導しようとした施設スタッフの手に嚙みついてけがをさせてしまう。
施設の看護師から向精神薬の処方について提案された。
スタッフが介護で苦労しています。徘徊の対応だけでも大変なのに、介護拒否や暴力行為もあって、このままではケアが継続できない。ご家族も疲弊していて、向精神薬の処方に同意されています。ご本人は病識がないし、これ以上は私たちも限界です。
ケアできないなら、最初から受け入れるべきではなかったのではないか。
そんなことを言ってみても彼女が救われるわけではない。彼女の自宅は家族によってすでに売却手続きが進められ、彼女が帰れる場所はもはや存在しないのだ。
食事、服薬支援、排泄、入浴、更衣・・・ここで必要なケアが受けられなければ、彼女自身の不利益も大きくなる。やむなく鎮静作用のある向精神薬を処方した。
2週間後の定期診療日、彼女はおとなしく椅子に座っていた。
体調はお変わりないですか? そんな問いかけに無表情で目線を合わせることなく、小さくうなずいた。とりあえず落ち着いています。看護師は経過についてそれだけ報告すると、向精神薬の処方継続を求めた。
その夜、彼女は自室で転倒し、大腿骨を骨折した。
薬でぼんやりした頭で、それでも家に帰ろうとしたのかもしれない。薬が奪うのは意思表示能力だけではない。判断力やバランス機能・姿勢反射を低下させる。薬が転倒の直接の原因だったのかはわからない。しかしそのリスクを高めたことは確かだ。
6週間後、彼女は病院から施設に退院してきた。
ご家族と会えたのは入居時以来。彼女が施設で苦しい思いをしてきたことをご家族に改めて伝えた。この骨折という事件も、不慮の事故というよりは、彼女が自分の想いを誰かに伝えようとした結果なのかもしれないと。
「家に帰りたい」という気持ちに蓋をすることはできない。薬を処方することは彼女の口を塞ぐこと。自分の想いを誰にも伝えることができない状態で、身も心も死ぬまで閉じ込められている。そんな人生が彼女にとって幸せだろうか。
その問いかけに長男一家は沈黙した。
その時、18歳の彼女の孫娘がこう提案した。
おばあちゃんは、もともと外出よりも家にいるのが好きな人。
だから、おばあちゃんの家をまるごとここに持ってきちゃえばいいんじゃない?
彼女の家の売却が決まり、家財の処分が必要なタイミングだったこともあり、孫娘の無邪気な提案は家族にもスムースに受け入れられた。翌日には彼女の個室から半透明の衣装ケース群が撤去され、彼女が1日のほとんどを過ごしていたというリビングで使われていたソファセットの一部とサイドボード、使い古された冷蔵庫、たくさんの本や雑貨が運ばれてきた。カーテンも彼女自身がオーダーしたという自宅で使われていたものに取り換えられ、若いころに3か月かけて作ったパッチワークのベッドカバーも持ち込まれた。お気に入りだったというウィッジウッドのティーセットも。
一回り小さくはなったが、そこに再現されたのは彼女が時間をかけて築いてきた「主婦の城」だった。彼女が長年親しんできた心地よい風景、そして慣れ親しんだ生活の匂いがそこにはあった。
彼女は自分を取り戻した。
家に帰りたいという要求はなくなり、夜間の中途覚醒も少なくなった。
もはや出口を探しに行く必要はないし、監禁者から身を守る必要もない。
彼女はようやく「家」に帰ってくることができたのだ。
向精神薬を減量しても彼女は穏やかさを失うことなかった。
薬を完全に中止して2週間後。
診察のために部屋を訪問すると、化粧をした上品な女性がソファに座って、紅茶を準備して僕を待ってくれていた。
明日は七夕ね。
私はまた主人と会えたら。毎年そう願っています。
先生はどなたとお会いになりたいの?
「徘徊する重度認知症患者」ではない、80余年の人生を丁寧に生きてきた一人の女性がそこにはいた。こんな素敵な女性に無作法にも向精神薬を投与した自分の不勉強を恥じるとともに、「いるべき場所にいられること」の重要性を認識した。それは「あるべき自分」を守るために極めて重要な前提条件なのだ。
異常行動と表現されることも多い認知症の人のBPSD(行動心理症状)にはそれぞれ理由がある。その多くは環境の不適合からの逃避行動だ。出口やトイレを探すために廊下を歩けば「徘徊」、無理やり服を脱がそうとされることに抵抗すれば「入浴拒否」、排泄の失敗の違和感を自分で処理しようとすれば「弄便」「不潔行為」・・・その人の行動の異常性を問題にすることはあっても、その人をその行動に駆り立てている要因については十分なアセスメントが行われないことがいまだに少なくない。
バリアフリーや十分な照度などは安全管理のためには重要だ。しかし最も優先されるべきは、その人が心地よいと思える、違和感なく過ごせる場所であること。こちらの考える「安全・快適」を押し付けるのではなく、その人にとってそこが自分の「いるべき場所」であると感じてもらえることではないか。
ユニバーサルデザインは大切な概念だ。しかし私たちは個々に心地よさ、使いやすさを感じるポイントが異なる。それぞれの目的に応じたパーソナライズされた環境、そこに暮らす人、それを使う人が調整できる余地、パーソナルデザインこそが重要なのではないか。
人生100年時代。誰もが(そうなる前に突然死でもしない限りは)最後の数年間は身体機能・認知機能の低下とともに生きることになる。
これを悲嘆のプロセスにしないために大切なことは何だろうか。
デンマークの高齢者政策委員会(Commission on Aging/Jørn Henrik Andersen委員長)が1979年から3年間の議論を重ね、高齢者福祉政策の3つの原則を次のようにまとめている。
1.生活の継続
高齢になってもできるだけ住み慣れた地域・家庭で、「自分らしい暮らし」を続けること。
高齢者介護はその人の選択した生活・人生」を最後まで支えていくことにある。
2.選択の尊重
その生活や人生は、高齢者本人が望む生活のあり方を尊重すること。サービス提供者や家族が一方的に決めてはならない。
3.残存機能の活用
介護は「できないことを代わりにする」だけではなく、「まだできることを生かす」視点で支援すること。そのために「自分でできることをやらせる」ではなく「本人の『強み』が発揮できる環境を整える」という発想がより重要。
重要なのは環境なのだ。
環境には、物理的な空間としての環境と、そこに関わる人間関係・コミュニティとしての環境がある。ケアの現場においては後者の重要性が強調されることが多いが、生活空間としての環境の影響も非常に大きい。
住み慣れた自宅においても、生活力の低下に応じて、その時々の人生の優先順位に応じた、その人の望む暮らしの継続を支えるための環境の調整が必要になる。
特に高齢者施設という空間では、そのコミュニティの一員であるというシチズンシップの獲得において、そこに自分の居場所=すまいがあるという物理的要素はより大きくなる。
齢を重ね、病気が増え、不可逆に心身の機能が低下し、最終的に死を迎える。
これは誰も避けることができない私たちの宿命だ。
それでもコミュニティとつながりを維持し続け、自分の強みが発揮できる環境の中で居場所や役割を見つけることができれば、たとえ身体機能・認知機能が低下したとしても、最後まで生きがいをもって生き続けることができる。
在宅医療を通じて、身体機能・認知機能の低下とともに生きるたくさんの人たちの人生の最終段階に伴走しながら、環境の持つ力を痛感してきた。
一人ひとりに最適なくらしのデザインが提供されれば、最後まで人生を謳歌できる豊かな超高齢社会が実現するのかもしれない。
「認知症の人をささえるデザインのちから」
間瀬さんにお声がけいただき、序文でそんな患者さんとのエピソードをご紹介させていただいた。
在宅医療に関わるようになって20年。
特に治癒を目指さない患者さんを幸せにするのは、医療ではないのだ、ということを日々痛感する。
生活モデルとは、ICFとは、つまり暮らしのデザイン。
人生をできるだけ自由にデザインできるように。
医者の出番は少し控えめくらいがよいのだと思う。
『認知症の人を支えるデザインのちから~からだとこころの変化を補い、暮らす環境を整える~』
間瀬 樹省, 山崎 正人, 山下 総司 (著)
https://amzn.asia/d/63fjQgM