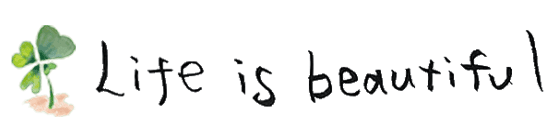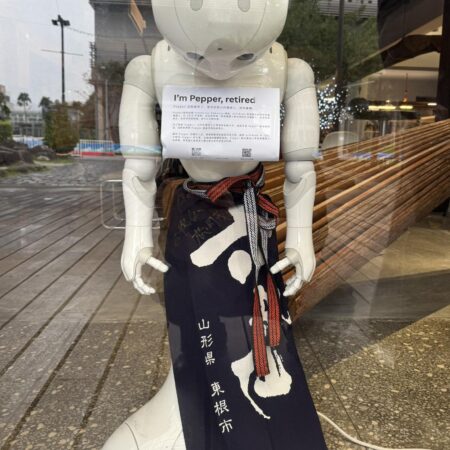終末期の点滴は「いい」のか、「悪い」のか。
点滴なんてしないほうがいい。
点滴するから食べられなくなる。
ある講演を聴講した。
点滴をやめ、大好きなものを口にして、うれしそうな患者さんの映像が流れる。
そして感動のコメントが溢れる。
でも、うんうんと素直に頷くことができない自分がいた。
そんな僕もかつては点滴忌避派だった。
「点滴はもういらない」
そんなタイトルの本を共著させてもらったのはちょうど10年前だ。
それまでは、在宅医療で食べられない人がいたら普通に点滴をしていた。
栄養を入れてあげたほうがいいかもしれない。
アミノ酸やビタミンが配合された末梢輸液製剤をよく使っていた。
一時的に食べられなくなった人でも、点滴でその間の命をつなぐことで、また食べられるようになることがある。
在宅医療を始めてから、そんな成功体験も重ねてきた。
だから、食べられない=とりあえず点滴をしよう。
最初のころはそんな在宅医療をやっていた。
そんな中、小川利久さんに出会った。
小川さんは特養で「自然な看取り援助」を実践していた。
老衰に伴って食事量が減っていくことは自然なこと、その経過を受け入れることで、穏やかな最期を迎えることができる。
確かにその通り。死が避けられない時は必ず来る。
そんな時に点滴をしても無意味だ。
点滴はしない、だけど丁寧にケアを重ねていく小川さんから、看取りとはこういうものなのだと感じた。
点滴をしなくてもいいんだ。頭ではわかった。
絶食状態においてはβエンドルフィンやケトン体が出現し、それが苦痛を緩和する作用があるということ、点滴をすることで平穏な最期が妨げられる可能性があるということ、欧米諸国においては終末期の点滴は時に虐待と認識されることがあるということ・・
特に終末期の点滴の功罪について学んだ。
点滴をしない、という選択にはそれでもぬぐい切れない違和感があった。
でも「科学的根拠」に基づいて実践してみることにした。
患者さんが人生の最終段階にあることを本人も家族も周囲も受容できているケースにおいて、敢えて点滴をせずに経過観察するようにした。
多くは穏やかな最期を迎えられた。
本人に苦痛症状は少なく、死前喘鳴も軽微で、文字通り、萎れた植物が枯れていくような経過だった。
そんな経験を重ねる中で、下河原忠道さんと出会った。
下河原さんは日本の高齢者ケアのあり方に強い違和感を持ち、自ら高齢者住宅事業に乗り出した社会起業家だ。
彼は、高齢者が最後まで生きがいをもって生き切れる理想の社会を、その人の主体性をケアで支える「すまい」を提供することで実現しようとしていた。
医療で生かされるのではない。
最後まで自分で生きる。
余計な薬は飲まない。
余計な点滴はしない。
本人の生命力が最大限発揮できる環境を整えることで、最後までその人の望む暮らしを支え続ける。
そんな運営方針と、それに呼応する入居者たち。
ここには今でも忘れられない患者さんがたくさんいるし、穏やかで満たされた旅立ちに何度も立ち会わせていただくことになった。
そんな二人にインスパイアされたのもあり、人生の最終段階の医療の在り方について問題提起する一冊を共著させていただくこととなった。
それが「点滴はもういらない」だ。
その後、臨床経験を重ねる中で、僕の考えは少しずつ変わってきている。
介護付き有料老人ホームに入居する高齢+終末期がんのある患者さんの看取りに関わる中で、施設の看護師さんからこう言われたことがある。
「先生が終末期に点滴をしない方針ということは理解しています。多くの人がそれで楽に過ごせることもわかりました。でも、この人には点滴をしていただけないでしょうか。この人はその方が楽に過ごせるような気がするんです。」
90代の悪性リンパ腫の女性だった。
食事はほとんど摂取できていない。尿量も減少しつつあり、日の単位だと家族には説明していた。がん性疼痛はほとんどなく経過をされていたが、確かに時折、眉間にしわをよせ少し辛そうな症状をしていた。
看護師さんの提案に従い、補液をしてみることにした。
1日に500ml。不感蒸泄でほぼ相殺されてしまう量だ。
しかしその後、彼女は穏やかさを取り戻した。
日の単位と予想していたが、その後3週間、比較的落ち着いた状態で過ごすことができた。家族は毎日のように訪問してくれて、週末にはお孫さんも集まってにぎやかに過ごされていたそうだ。
点滴をしなければ、食べられない人は枯れる。
しかし、それがその人にとって本当に枯れるべきタイミングなのか。
その見極めは本当に難しい。
中には根腐れをする人もいるかもしれない。
でもたとえ終末期であったとしても、少しの水分で潤いを取り戻し、本人にとっても家族にとっても、それが一時的なものであったとしても有意義な時間を確保できる人もいる。
終末期の点滴は「いい」のか、「悪い」のか。
こういう議論は不毛だと思う。
それはその時々の病態によって違うし、患者や家族の価値観や人生観によっても違う。そもそもそれが本当の終末期なのかどうかの判断も難しい。
僕はいま、点滴の中止(不開始)の判断については慎重だ。
患者本人が点滴は必要ないと意向表明しない(できない)状況において、点滴をしないという決断に懐疑的な意見があるなら、少量で補液を試してみてもいいのではないか。
痰が増える、吸引が増える、浮腫が目立つようになるなら減量・中止を検討する。それでもいいのではないかと思う。
大切なのは、点滴をするかしないか、ではなく、本人にとってその時点での最善の選択は何なのかを丁寧に考えることではないか。
また「点滴(または経管栄養)をするから食べられない」という意見についても、僕はそんな単純なものではないと思っている。
点滴(経管栄養)で食べていない人は、本当に食べられない人か、あるいは食べることのリスクが過大評価されているか、そのいずれかだ。前者であれば点滴をやめても食べられるようにはならないし、後者であれば点滴をしていても食べられる。むしろ脱水の補正がされていなければ唾液の分泌は減少、嚥下に悪影響を及ぼすし、食欲も意識レベルも低下する。適切な水分や栄養の補給は、むしろ食機能を回復するための重要な治療手段だと認識している。
大切なのは、個々の食べる機能の適切なアセスメントではないか。
好きなものなら食べられる、確かにそんな人もいる。
最後の思い出作りに好きなものを1つ口に含ませるだけなら、そんなチャレンジをしてみてもいいかもしれない。
でも、いわゆる「食べられる人」は少なくとも老衰の末期ではない。
補液を含む適切な栄養治療を併用しながら、食べる機能をきちんと評価しながら食支援を進めていくほうが成功率は高いし、本当に食べさせてあげたいと思うなら、そうすべきではないか。すでに確立された方法論があるのだから。
点滴や経管栄養を中止してみて「食べられたらそれでOK、食べられなかったら看取り」みたいなラフな判断で本当にいいのか。
10年前の僕なら素晴らしい!と拍手喝采していたかもしれないけど、食支援の部分についてはちょっと納得できなかった。
日ごろから食支援に関わっておられる方々がこの講演を聴かれたらどう思うかな。