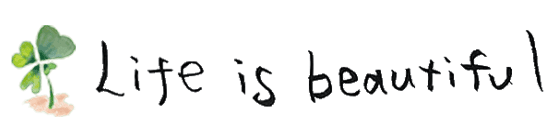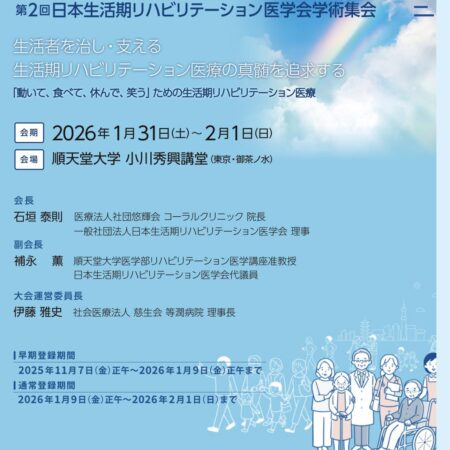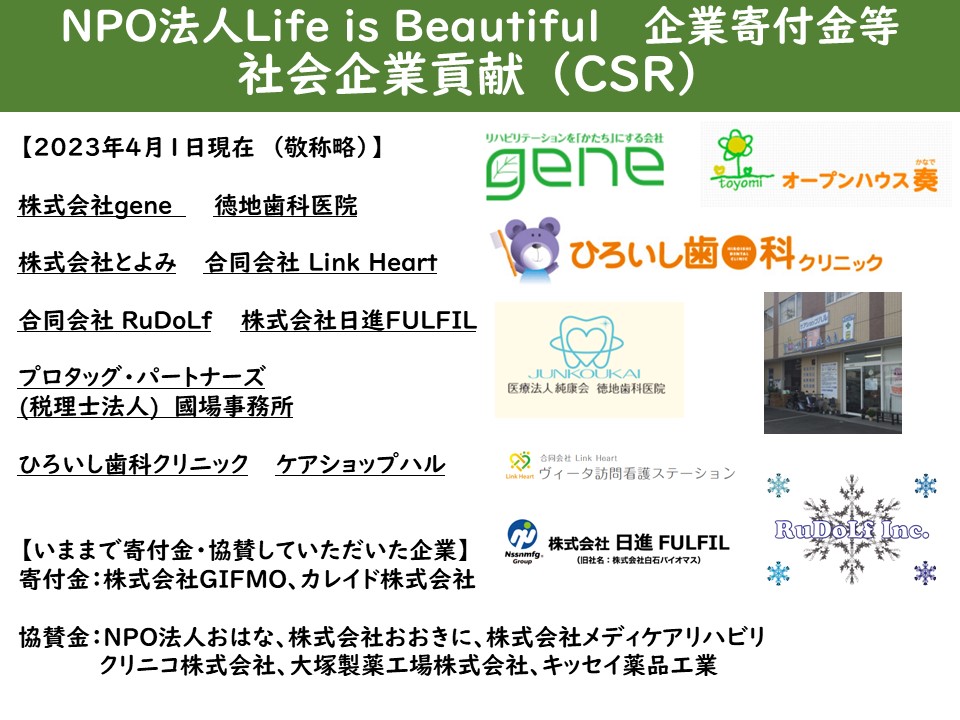自己負担の増加は「不要な医療の抑制」と「必要な医療へのアクセス制限」
若い女性が腹痛を主訴に救急車で来院。
昨夜は千葉市医師会の夜間救急診療担当でした。
整腸剤飲んでおなか温めて様子みてたらいいんじゃない、という感じでしたが、本人は本当に症状を心配している様子で、もちろん丁寧に対応しました。
僕が子供のころ、一番怖かったのが腹痛でした。
何が起こっているんだろう。死んじゃうんじゃないだろうか。
本気で心配だった。
消化器内科(おなかのお医者さん)を選んだのも、そんな幼少期の記憶に誘導されたのかもしれません。
医者の立場からすれば、なんでこんな軽微な症状で救急要請してるんじゃ!と思うかもしれないけど、本人にしてみれば、それが妥当な選択に思えることも多々あるはず。
もちろん指先に小さなとげが刺さったくらいで救急車を呼ぶのはどうかとは思いますが、問題の本態は「救急要請のハードルの低さ」というよりは「救急以外に相談窓口がないこと」なんじゃないかと思います。
家庭医・GPが制度化されている国々では、まあこういうことは起こらないんでしょう。制度の不備を棚に上げて、患者を批判するのはちょっと違うなと思います。
一部の自治体では、救急車を有償化するという取り組みが行われています。救急病院は紹介状を持たない、入院を要さない緊急受診患者に対してはプラスアルファの費用を請求することができるようになっていますし(選定療養)、救急車の有償化もその延長線上で理解すればよいのかもしれません。
しかし一方で、これが必要な受診の抑制につながり、結果として早期発見・早期治療ができず、重大な健康アウトカムの悪化や、より大きな社会保障費の支出につながる可能性も当然あります。
夜中にかかりつけ医が診療して紹介状を書くなんて、在宅患者さんくらいしかないと思うし、入院を要するかどうかなんて患者さんやご家族だけでは判断できません。
救急医療の最適化は、救急以外の医療アクセスの選択肢の確保とセットで行われるべきだと思うのです。
先日の日経には、特に経済弱者は自己負担が減ることで医療アクセスが改善するという東北大+九州大のプレスリリースが出ていましたが
https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP698601_X21C25A0000000
自己負担の増加は「不要な医療の抑制」だけでなく「必要な医療へのアクセス制限」という側面もあることを十分に認識する必要があると思います。