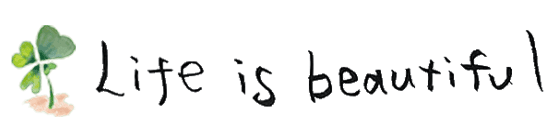社会にとって、未来にとって、最適な医療の形とはどのようなものなのか
医療における最大のステークホルダーとは?
それは医療機関?
それとも患者?
いや、「費用負担者」ではないか。
医療の費用の大部分(7~9割)を負担しているのは、実は保険者(+税金)だ。
この仕組みがなければ患者は必要な医療へのアクセスが制限されるし、医療機関も収入が保障されない。
今日は、京都の健康保険組合連合会にお声がけいただき、社会保険の持続可能性に関する2時間の講演とディスカッションの機会をいただいた。
主に大企業の従業員とその家族を対象とした健康保険組合。
若い世代が多いので、医療への依存度は低く、その多くは組合員を支えるだけなら何の問題もないという。
しかし、健康保険組合は、集めた保険料の半分を後期高齢者医療制度を支えるために供出しなければならない。
その関心のフォーカスは、組合員=現役世代の医療費ではなく、後期高齢者の医療費だった。
年々増大していく高齢者医療費。
なんとかやりくりしながらここまで来たけど、これ以上の拠出金の増加に耐えられるのか。少なくともこの伸びが続くのであれば、持続可能ではない。
そんな危機感をひしひしと感じた。
病気は加齢とともに増えていく。
だから、前期高齢者、後期高齢者と医療費が増大していくこと自体は自然なこと、というか、これはやむを得ない。
いまは病気が少ない若い世代も、自分たち自身がリタイアするころからがんや脳卒中、心筋梗塞など大きな病気を発症するリスクが急速に高まっていく。しかし収入は少ない。結果として費用負担能力のある人たち、その多くは若い世代からの「仕送り」に依存せざるを得ない。
自分たち自身もそうしてきたわけだし、これからもそうしていくしかない。
人口が減少していく局面で、増大する高齢者を支え切れない、という意見もある。
しかし、テクノロジーの進化によって医療のトータルコストは大きく下げられる可能性もある。
例えば、HCV,HBVが完治するようになって肝硬変や肝細胞がんは大幅に減ったし、HPVワクチンが普及すれば子宮頸がん治療が必要になる人は大幅に少なくなる。一時的に支出は増えるものもあるかもしれないが、将来のとタールコストを下げるような画期的な治療技術がどんどん実用化されている。
ナッジを活用した治療アプリなどが実用化されれば、生活習慣病の増悪による動脈硬化性疾患や腎不全を減らせるかもしれない。
また(例によってポジショントークと言われるとは思うが)在宅医療を機能させることも、社会保障費の伸びを抑制する上で重要だと思う。
特に後期高齢者のうち超高齢者(85歳または90歳以上)については、医療費を大幅に削減しうるのではないか。
いまこの集団は一般急性期入院の約1/3を占めている。そしてこの集団の医療費の支出の8割は入院によるものだ。
その入院理由の大部分は肺炎や尿路感染などの感染症、そして心不全など加齢に伴う機能低下が背景にある。骨折であれば、手術適応になる場合も少なくない。しかし、それ以外の疾患の多くは入院をしなくても在宅での治療が十分に可能ではないか。
そして自宅での治療は、病院での入院のように機能低下を伴いにくいのではないか。
台湾では、肺炎・尿路感染・軟部組織感染症(蜂窩織炎)の3疾患について、在宅での急性期治療を制度化した。DPCのような包括報酬と効果的な治療に対するインセンティブを導入することで、一般の病院入院に比べて、入院期間を2/3に、入院費用を1/3に削減、再入院率や死亡率は病院入院と差はなかった。何より患者・家族の満足度は100%だという。
私たちはインドで、肺炎や消化管感染症、デング熱などに対してやはり在宅入院のサービスを提供している。看護師による連日の訪問で治療を行うのだが、その80%は自宅で治療を完遂できる。そしてここでも患者満足度は高い。
ここでもテクノロジーの進化が効果的なケアを支える。
老々世帯の自宅でも、遠隔モニタリングのためのベッドセンサーを導入し、訪問看護が24時間対応することで、安全には肺炎の治療が行える。
重度のケース以外は自宅や施設でケアができる体制を整えることで入院依存を大幅に下げることができると思う。
そんな資源はないと言われるが、看護師を病棟から地域にシフトすることができれば、十分に対応は可能だ。
テクノロジーの進化は医療の侵襲を減らし、入院への依存を減らしている。現在の多くの病院の赤字の主因である「入院患者数の減少」は、病院のサービスの問題ではない。患者数の減少×入院依存の減少という社会の変化の結果だ。
既存のベッドを温存するために診療報酬を手厚くしても、そのベッドは空床のままだ。
実態的ニーズに応じたベッド数に弾力的にダウンサイジングを検討すべきではないか。
同時に機能の集約化も進め、より合理的・効果的に、より高品質な専門的ケアが継続的に提供できる体制を確保すべきではないか。
医療ニーズよりケアニーズのほうが大きい集団に対しては、急性期も含め、病院医療ではなく在宅医療・ケアを中心に対応すべきではないか。
そしてプロセスに対する出来高ではなく効果的な医療に対してインセンティブ、疾患ごとのDPCというよりも、再入院や死亡率も加味したバンドルペイメントを検討すべきではないか。
いろいろな意見が出た。
財源が足りない、でも国民はこれ以上の社会保険料や消費税は払いたくないと意思表示している、そんな中で医療改革をすどう進めるのか。
費用負担者としての健康保険組合は、いまのところ穏やかに国の方針に従ってくれている。しかし、そのお金の使い方にいつまでも黙っていてくれるとは限らない。
社会にとって、未来にとって、最適な医療の形とはどのようなものなのか。
中医協では医療保険制度の増改築が今まさに議論されている。しかし、本当はゼロベースで考えなければいけない時が来ているのではないかと思う。
会を終えて懇親会。
美味しい土瓶蒸しをいただきました。
貴重な機会を頂戴しました京都健保連の皆様、ありがとうございました。