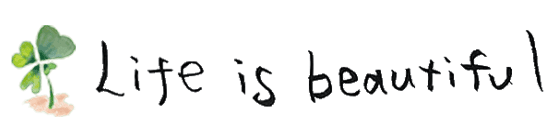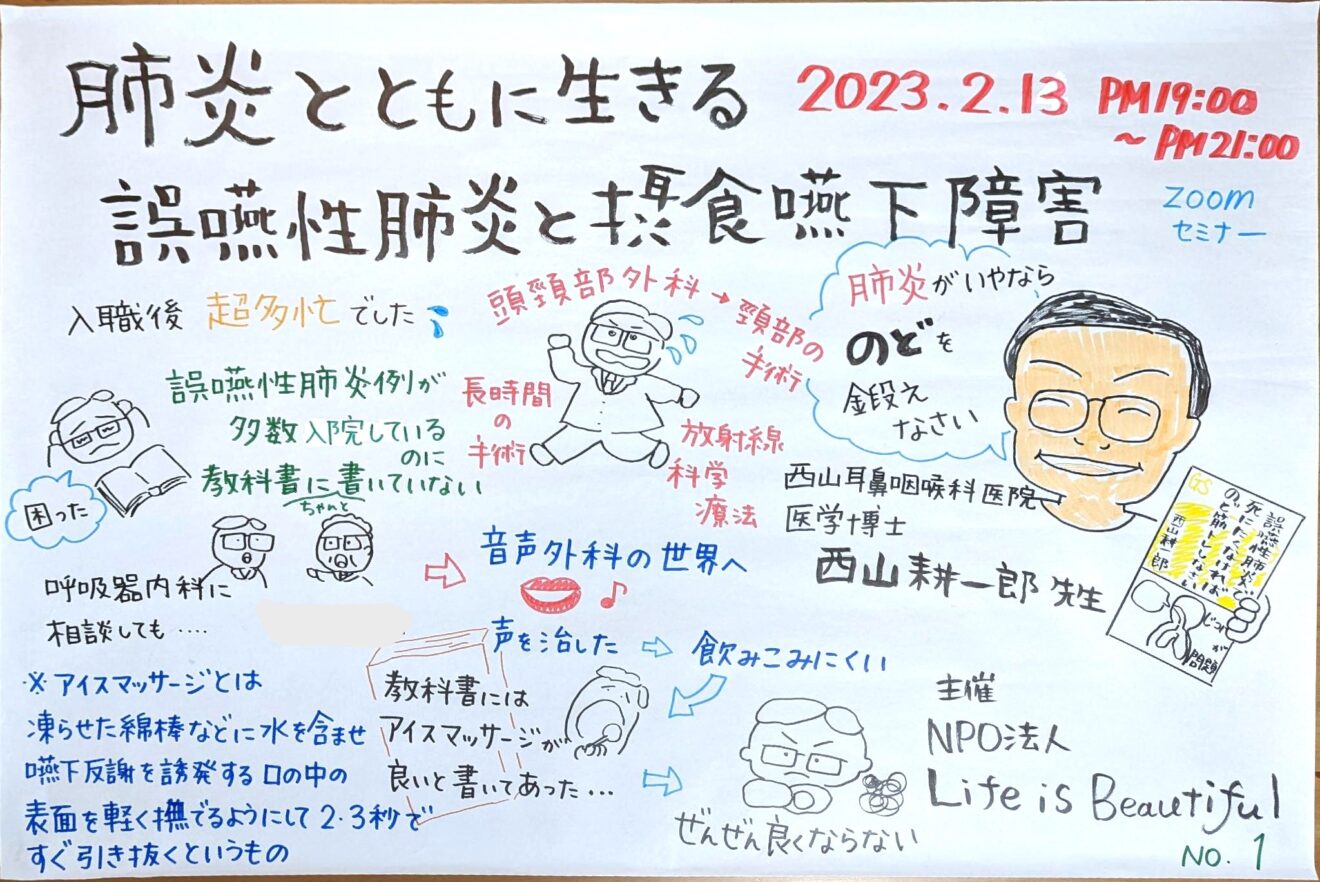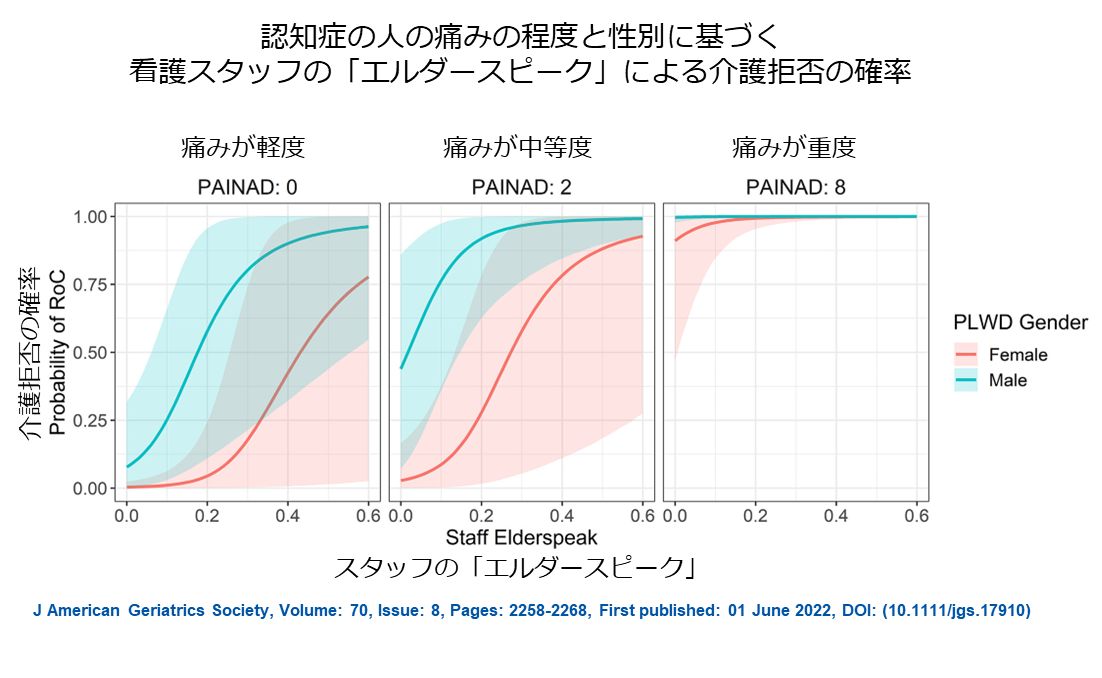余命3か月といわれたら
余命宣告は残酷なことに思える。
しかし実はそれは「死を覚悟せよ」という意味ではない。
「余命3か月といわれたらどうしますか?」
先々週末、京都で緩和ケア医の四宮先生に模擬宣告をしてもらった。
がん治療中の患者の息子という立場でのロールプレイだったが、もし自分がそう宣告されたらどうするだろうか。そんなことを考えていた。患者役の武田イチロー先生は「ロールプレイとはわかっていたが、宣告された瞬間、頭が真っ白になった気がした」そんな感想を述べておられた。
子供のころは「死ぬ」ということが本当に怖かった。
漠然と100歳になったら死ぬと思っていて、自分や家族はあと何年生きられるのか、勝手に余命を計算して一人で悲しい気持ちになったりしていた。
その後、医師になった。
最初に受け持った患者さんとの死別はいまでも明瞭に覚えている。多発性骨髄腫の50代の女性だった。化学療法を繰り返し、自宅にはほとんど帰れず、最期を病院で迎えた。これ以上治療ができないんです。そう伝えたときの彼女のきょとんとしたような、そしてその直後に見せた悲しそうな表情は脳裏にはっきりと焼き付いている。治療を継続するために僕は彼女と「きっと次の治療はうまくいく」という「最善への期待」を共有しつつ「もし治療がうまくいかなかったら」という「最悪への備え」ができていなかった。その1か月後、彼女の最期の言葉は、それでも僕に対する感謝の一言だった。僕は涙を流した。というか号泣した。彼女の夫がベッドサイドで泣き崩れる僕の肩をそっと抱いてくれるという体たらくだった。
それからたくさんの患者さんたちとお別れしてきた。患者さんの人生に深く入り込むと自分が苦しむ。少しずつ死別を客観視するようになった。
死ぬとは生命活動の終焉。その人の存在がこの世から消えてしまうこと。だからこそ死を回避することが何よりも重要なのだ。そのために医療が果たすべき責任は大きい。病院で仕事をしているときはそう考えていた。
その後、在宅医療の道に進んだ。
そこでもたくさんの人の死にざまに立ち会ってきた。
そこでは、何よりも忌避すべきものと思っていた死と正面から向き合い、医療に依存せず、積極的に生き方を選択する人たちに出会ってきた。
長く生きることに固執せず、自分の人生を完成・完結させることにこだわりたい。
昨年逝去した叔父はそうはっきりと自分の想いを言葉で伝えてくれた。
治療を中止し、信念を貫いて旅立たった彼は、いまも彼と関わったすべての人の心の中で生き続けている。
死ぬとは存在の消失ではない、人生の1つの区切りに過ぎないのかもしれない。大切なのは死なないこと、ではなく、今いる場所で死ぬまで自分らしく生きること。死に対する考え方は在宅医療を通じて大きく変化した。
余命宣告は一見、残酷に思える。
しかし「それは死を覚悟せよ」という意味ではない。
残された時間を伝えることで、その人は、人生を完成させるための計画を立てることができる。やっておきたいこと、やっておかなければならないことを明確にし、優先順位を考え、取捨選択し、本当に大切なことに残された時間と体力を集中できる。
死を避けることができないのは誰も同じだ。
残された時間がわかるのか、わからないのか、違いはそれだけだ。
死が避けられないのであれば、それを避けるために時間と体力を使うより、残された時間を自分の人生にとって納得できる形で使ったほうがよいのではないか。
そう思えるようになるには時間もかかる。
そしてそこからの時間はできるだけ長いほうがいい。
きっと治療はうまくいくはず。治療が失敗するはずがない。
そんな期待をするなというつもりはない。
しかし、うまくいかなかったときにどうするのか、考えておくことも大切だ。
最後の治療の選択肢がうまくいかなかったとき、「あと3か月」と突然宣告されるより、もしこの治療がうまくいかなかったら、あと半年くらいかもしれない、と少しでも早めに教えてもらっておいたほうが運命を受け入れるための時間も、人生の計画を実行するための時間も確保しやすい。
緩和医療の世界には「最善に期待し、最悪に備える」という有名な言葉がある。
最善とは治療がうまくいくこと、最悪とは治療が失敗し死んでしまうこと。そんな解釈が一般的だ。
だけど死は誰にとっても避けられない。死を「最悪」とするなら、私たちの人生はみなバッドエンドということになる。
僕は、最善とは最期まで自分の人生を生き切れること、最悪とは最期まで医療に人生の所有権を奪われ自分の人生を完成できないことと解釈すべきだと思う。
医療ではどうにもできない人生の長さがある。
だからこそ、与えられた時間の中で自分の納得のできるスクリプトを完成させる。
そんな支援こそが緩和ケアに求められているのだと思う。