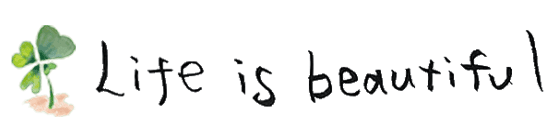開業当初。
佐々木理事 2023年 4月16日 Facebook記事より
開業当初。
医師会や学会の重鎮の先生方から「お前のところの在宅医療は質が悪い」「ちゃんとした在宅医療ができていない」などの批判をいただくことも少なくなかった。いや、自分たちは誰よりも頑張っている。そんな自負はあった。
だけど反論できなかった。
「質の良い在宅医療」とは、「ちゃんとした在宅医療」とは何なのか?
自分たちできちんと言語化できていなかった。それをきちんと説明してくれる人もいなかった。
そこで僕たちは、自らの在宅医療の質に関する指標を複数設定し、それらを継続的に計測しつつ日々PDCAを回すとともに、そのデータを(患者さんからのネガティブなコメント等も含め)すべて公開してきた。
腰に不安のある週末。ようやくまとまった昨年度の年次報告書の試し刷りを眺めながら、改めて在宅医療の社会的生産性と質の可視化について考えてみた。
ーーー
若い人の病気は、治療することで生産人口に戻す、社会の支え手として再び機能させることができる。急性期医療の社会的コストの合理性を説明するのは容易だ。
しかし、在宅医療にはそのような「治療力」はない。きちんとした在宅医療が提供されれば、患者は長く生存できるが、そのためには医療だけではなく介護のリソースも必要になる。頑張れば頑張るほど、社会の負担が大きくなる。そんなジレンマを抱えている。
いずれ死ぬ高齢者のために、きちんと医療を提供する必要などないのではないか。コロナ渦においては、そんな辛辣な言葉を何度もぶつけられた。
そもそも在宅医療の価値はどこにあるのか。
2つの存在意義があると僕は考える。
1.在宅医療が充実することで、生活の質が向上する在宅医療には病気を治す力は弱い。
しかし、「病気や障害とともによりよく生きる」を支えることはできる。足が動かなくても、食事や呼吸ができなくても、医療機器や支援機器を活用しながら、雇用や納税を通じて社会の支え手として機能し続けている障害者も少なくない。
テクノロジーが進化すれば、医療や介護を社会復帰のツールとして使いこなせる人が増えていくかもしれない。また、人生の最終段階にあっても、最期まで納得して生き切れることができる。
そんな支援が受けられるなら、国民の多くも将来の受益者として、その社会コストに対して納得してくれるはずだ。
大切なのは「要介護状態で生かす」のではなく、「本人のQOLを最大化する」こと。
自立支援という目的共有ができれば介護保険サービスとの連携も効果的を発揮するはずだ。健康寿命を守る急性期医療、社会参加寿命を延ばす在宅医療。
「支えるVS支えられる」ではない支え合うコミュニティという概念が広がれば、社会の中で在宅ケアはよりポジティブな位置づけにできるはずだ。
2. 在宅医療が充実することで、医療資源の適性利用化が進む。
在宅医療をきちんと機能させれば、救急搬送や入院医療への依存度は大きく下げられるはずだ。悠翔会の場合(2021年度実績)在宅管理患者の年間平均入院日数は13.1日。一方、当院の患者の在宅医療導入前の1年間の平均入院日数は41.2日。在宅ケアを提供することで患者一人あたり年間28.1日、入院を削減している。悠翔会の担当患者数は法人全体で約7500人。つまり年間延べ21万日分の入院を削減していることになる。後期高齢者の1日あたりの入院コストは平均3万円程度。入院医療費にして約63億円分ということになる。
これは当法人の年間診療収入を大きく上回る。つまり在宅医療は入院医療費の削減を通じて、社会保障費の「節約」に貢献できるかもしれないということだ。在宅医療の診療収入が、入院医療費の削減分を超えなければ、少なくとも「余計な医療費」と揶揄される筋合いはない。
この63億円を患者一人あたりで計算すると84万円/年、月7万円という結果になる。これは実は概ね月2回の訪問診療の診療報酬に相当する。厚労省が意図したものなのか、偶然の一致なのかはかわらないが、救急搬送や入院をきちんと抑制するのであれば、在宅医療はその診療報酬について社会に対し説明責任を果たせるということになる。
ただ、そのためには「在宅患者一人あたり年間30日の入院日数削減」程度の予防医学的介入+急性期の在宅対応力が求められる、ということになる。
ーーー
在宅医療の質を可視化すべき在宅医療には2つの価値観がある。
1つは「医学モデル」としての在宅医療だ。
すなわち、併存疾患をきちんと管理し、予測される急変に対し予防的・予測的に対応し、急変しても自宅できちんと診断と治療ができること。私たちは、この医学モデルの指標として、以下の3つを評価対象項目として追跡し、改善のために各自がフィードバックしている。しかし、実はそれぞれの項目を単独で在宅医療の質として評価することは難しい。
① 看取り数(看取り率)在支診の施設基準の1つでもある重要な指標だが、これは在宅医療の成績というよりは、最期まで生活を支えることができた在宅ケア・多職種によるチームケアの総合成績というべきもの。
もちろんチームづくりへのコミットメントも含めて在宅療養支援診療所の果たすべき役割だが、クリニック単体の診療の質の指標としては単純化しにくい。
② 急変の頻度(電話再診件数・往診件数)在支診の施設基準では往診件数をアウトカムの指標として評価している。確かに時間外に往診ができることは機能として必要不可欠だ。
しかし、もっと重要なのは急変をさせないことであるはずだ。往診ができることを評価するのはよいが、急変が多いことは評価できない。しかし、急変の頻度は「電話再診が少ない」のか、「そもそも電話対応をしていない」のか区別が困難であるため、アウトカムの指標として医療機関間の比較には使いにくい。アウトカムというよりはプロセスに分類されるべきものなのかもしれない。
③ 入院の頻度・入院日数入院は、「急変」とは異なりデータとして安定している(ごまかしがきかない)。社会保障費に与えるインパクトも大きく定量化もしやすい。
また、入院は患者の身体機能・認知機能に大きな影響を及ぼす。悠翔会の管理患者の緊急入院について調べてみると、誤嚥性肺炎で入院すると要介護度が平均1.72悪化、骨折で入院すると要介護度が平均1.54悪化していた。
入院関連機能障害を抑制する=患者のADL・QOLを守るという視点からも、入院の抑制をアウトカムの1つに設定することは非常に合理的であると思う。
入院を抑制するためには、日常の医学管理の質、急変時の在宅対応力、終末期の意思決定支援の3つが必要であり、在宅医療の機能を包括的に評価しうる。
そして、もう1つの側面が「生活モデル」としてとしての在宅医療(在宅療養支援)だ。
患者の病気や障害を医学的に管理するにとどまらず、病気や障害があったとしても、望む生活を実現できるよう環境因子に多職種とともにアプローチするとともに、人生の最終段階においても最期まで納得して生き切れるよう支援していくこと。
これこそがもっとも重要な在宅医療の仕事だと僕は思っている。
しかし、そのゴールや目標は患者ごとに異なる。それぞれの患者に最適な選択を支援し、選択された生活が実現できているのか、それを評価しうる汎用化できる指標があるのか。
悠翔会では現在、患者・家族および関わる多職種に定期的にアンケートを実施し、NPS(Net Promoter Score)を用いて定量化することを試みている。ご存じの方も多いと思うが、NPSはサービス業における顧客の継続利用意向を知るための指標として用いられるもの。10段階評価のうち、上位2段階(9点・10点)を選択した人を「推奨者」、6点以下を選択した人を「批判者」とし、推奨者の割合から批判者の割合を引いたものをスコアとする。推奨者が相対的に少なく、批判者の割合が多いクリニックは、患者支援において改善の余地が大きいということになる。
また、どの部分を改善すれば、NPSは上がるのか。患者や連携事業者にはNPSとは別に13項目の質問を行っている。それぞれの項目や患者・事業者からのコメントを読み込むことで、自分たちの診療のどこにのびしろがあるのかを知ることができる。ちなみに悠翔会の21クリニックで実際に評価をしてみると、当然ながらNPSと新規の紹介患者数は相関する。
ーーー
質の評価に関する議論これらのKPIは、もちろん公的なものではない。
悠翔会においても試行錯誤のプロセスにあるものだ。しかし、在宅医療も保険診療である以上、その費用に対してどのようなレベルの医療が提供されるのか(されるべきなのか)、明示する努力をすべきであると強く思う。
ナラティブや「寄り添い」はもちろん大切だが、それはあくまで在宅医療者に求められる最低限の「態度」である。
保険医療としてはきちんと定量化できるアウトカムを示す必要がある。
現在はストラクチャー(施設基準や連携体制など)やプロセス(往診件数や施設患者の割合など)だけで評価が行われている。
本来であれば、目指すべきアウトカムを達成するために、ストラクチャーやプロセスがどうあるべきかの議論がスタートするのではないだろうか。
コロナ禍で国民は医療費に対して具体的な関心を持つようになった。今後1割負担が2割、3割と上がっていけば、その高額な医療費に対してどのような価値が提供されるのか、さらに関心は高まっていくはずだ。社会保障財源が逼迫していく中、保険医療者は自らの「取り分」の守るためにも、費用負担者に対して受け取る対価(診療報酬)の妥当性に説明責任を果たす覚悟が必要だ。
そして、適切な医学管理をしていない、休日夜間対応をしない、看取りをしない、地域の事業者と連携しない、そのような同業者に対しては自浄作用を発揮しなければならない。
そのためにも、学会や業界団体は在宅医療の質の均てん化に取り組むべきだし、観念論ではなく具体的かつ定量が可能な質の指標を明示すべきではないだろうか。
もちろん自分たちがベストであるとは全く思ってもいない。在宅医療がどこまでできるのか。一昨年の夏、ワクチン未接種のコロナ肺炎患者の生命を守るために戦った経験は、自分たちの「常識」を壊すよいきっかけでもあった。さまざまな社会保障のリソースとのバランスと、地域ごとに自ずと生じる最適な役割分担の中で、境界線を設定せずにこれからもチャレンジを続けていきたい。