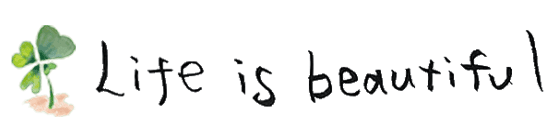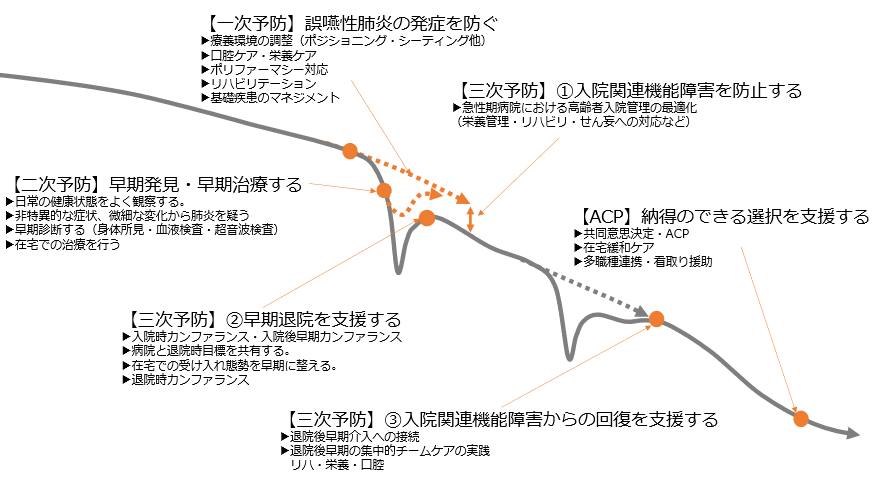「家族」はケアにどう関わるべきなのか。
佐々木理事 2022年9月8日 Facebook記事より
ケアプランを考える時、「ご家族に方に頑張ってもらって・・」というスタンスのケアマネさんは多い。
しかし、日本の介護保険制度は、超高齢化と核家族化が進行する中、家族に依存しない介護、「介護の社会化」を目指したものであったはずだ。
もちろん困ったときに家族として関わる。これは介護のあるなしに関わらず、家族としての役割であっていいと思う。
しかし、長く続く両親・祖父母の介護のために若い世代が離職・退学、ということもまだまだ普通に起こっている。これは家族のこれから先の人生の質に大きな影響を及ぼすし、社会の生産性も低下させる。こんな事例に触れるたびに、介護保険制度の一端で仕事をしている立場としては本当に申し訳なく思う。
家族がどのようにケアに関わるのか。これは、今回のドイツ見学の関心の1つのフォーカス。勝手に見たこと、思ったことをまとめてみた。
●家族介護に対する現金給付
日本では家族介護は、あくまで家庭内のマター。
しかしドイツでは、家族によるケアも制度でカバーされる。家族が在宅ケアを担う場合、それに対して現金の給付が行われるのだ。
1週間に2回以上、少なくとも10時間以上、家族の介護に従事すれば、例えば要介護2だと月額で316ユーロ(4.6万円)、要介護5だと900ユーロ(13万円)受け取れる。また、介護者には労働保険のカバー、減税や年金保険料の介護保険からの支払い、低金利の貸付制度などの補助もある。
僕は、日本でも家族ケアを評価する仕組みがあってもよいのではないかと考えていた。
しかし、ブレーメン市の認知症施策を担うペトラ・ショルツさんは、家族介護は本人にとってあまり望ましくないこと(その質にばらつきがある)、現金の給付額は通常の労働と比較して単価が安く、特に若い世代の生活は事実上成り立たないこと。そして家庭の中では女性がケアを担うことが多く、この制度があることによって、女性が介護労働に縛り付けられてしまう傾向があることが非常に問題である、と指摘した。
専門性をもった介護職が不足する中、高齢化していく地域をどう支えるのか。
家族を「介護労働者」にすることは、たとえそこに対価が発生したとしても必ずしも本人・家族の双方に好ましい結果を生まないことを理解できた。
特に認知症ケアにおいては、敢えて家族が関わらないほうが、本人は穏やかに過ごせることも少なくない。
家族に過度の負担をかけないケア。
それを実現するために必要なのは、「家族的な関わり」以外の部分を補完できる地域や専門職の関わり。
そして、何より本人にとって、より安心できる、よりスマートなケアを実現する生活環境。
家族の介護力に依存するのではなく、地域の潜在能力を引き出すこと、専門職と地域の最適な役割分担を考えること、そして、本人がその残存機能・強みを最大限発揮できる環境を整えていくこと。
人材も財源も厳しいが、日本のケアの現場にも伸びしろはまだまだあると思った。
●「家族」の定義
ドイツでは(そしておそらくドイツ以外のヨーロッパの国々でも)「家族」は血縁関係に限定されない。
内縁や事実婚、友人なども家族として認められる。
日本でも意思決定において「家族等」という表現が使われるようになったが、血のつながりよりも、実際の生活のつながりのほうがより重要であることは、ケアの現場でもしばしば経験することだ。
ドイツでは、家族と利害が対立する場合、本人が選んだ相手が(法的責任と権限をもって)重大な意思決定の支援をすることもできる。また、そのような相手を自分で選択できない場合には、後見人制度が活用できる。ドイツでは100万人が市民後見人としての活動をしているという。この市民後見人を支援(研修・マッチング)する仕組みも制度として整えられている。マッチングにあたっては、双方の人となりの理解と、実際の面会と、双方の合意が必要になる。一方的に誰かにあてがわれた人が後見人をするわけではない。そして、裁判所で定められた範囲で、後見活動を行い、それを裁判所に報告する義務を負う。
日本では、近くの友人よりも、遠くの血縁家族の判断や関わりが優先される。これが時にその人の人生の質に大きな悪影響を及ぼすことがあるのは、おそらく医療ケア業界で働く誰もが一度は経験している。
遠くの血縁関係も使えない場合には、弁護士や行政書士などがその任を担うが、医療やケアの方針を共に考えるパートナーというよりは、資産管理人としての位置づけだ。そして時に後見人は、面倒な意思決定に巻き込まれる、あるいは生活上のトラブルへの対応を減らすため、本人の経済力の範囲で、本人の望まぬ場所に転居(施設入所など)させてしまうこともある。本人にとって本当に必要なのは、資産を守ることではなく、納得のできる人生を送ることであるはずなのに。
ドイツでは市民後見人たちは、本人の友人のように関わり、お茶を飲んだりしながら、その人と対話を重ねていく。まさにこれはACPそのものだ。高齢者の多くは、専門家(士業)による貢献よりも、より対等に対話ができる市民後見人を好むという。
その人にとっての「家族」とは誰なのか。
血縁の近い順に「キーパーソン」を勝手に設定するのではなく、その人の生活の中でのつながりをしっかりと把握し、その人が納得して生活が継続できる、納得して人生が選択できる、そのパートナーとして誰がふさわしいのかを本人の意向も大切にしながら選択したいと思った。

●家族たちが自らつくるケアサービス
一方で、家族による積極的な関わりの形もある。
それは介護労働をする、という意味ではない。家族がよりよいケアの環境を自ら作り出す、という意味だ。
初日の午後に訪問したWOGEは形態としては認知症グループホームだが、そのスタートは、認知症ケアに関わる家族や友人たちが一緒に作ったいわばシェアハウス、コーポラティブハウスだ。
認知症があっても快適に、安心して暮らし続けられる「すまい」。
家族はそのケアに介護労働として関わることはできないが、家族の一員としてつながりを維持する。お互いに最適な頻度で施設を訪問し、自宅の一室のようにコーディネートされた個々の居室の中でゆっくり話をして、あるいは庭先でお茶を飲みながら、「家族の時間」を過ごす。
共用部分(リビング・ダイニング・キッチン)のインテリア、バルコニーの植栽や花などは、家族が集まって一緒に考える。提供されるケアの質、提供される生活支援の質(食事・清掃・洗濯など)を家族がきちんと評価し、必要に応じてサービス事業者を選択・変更する。
そのために家族は月に1度ずつ集まる。家族の認知症ケアという課題を共有するそれぞれのご家族も当然、みんな仲がよく、それぞれの家族間でもお互いに困ったことを支援し合う。
専門的なケアの提供、生活支援の提供はプロにまかせ、家族として最適なケアの在り方を考え、そして家族として支え、家族間でも支え合う。
誰のための、何のためのサービスなのか、というのが明確だし、それにかかるコストについても、公的負担でカバーされない部分は、家族が自分たちで拠出し合う。フォーマルとインフォーマルが、仕組みの上でも財源の上でも合理的に組み合わせられている。
日本でもこのような取り組みは少しずつであるが広がっている。
市原さんたちがやっている宮崎の「かあさんの家」などがそれだ。
制度に位置付けられたものではないが、その運営においては公的サービスをうまく組み合わせながら、その人にとって最適な「くらし」を実現しようとしている。
WOGEではほとんどの人が、この場所で人生を終える。
人生の最期まで「生活を継続」するための場所なのだ。
日本では空間的に画一的な医療・ケア施設が多い。
ケアの質も、「事故を起こさないこと」などのプロセスが主たる評価の対象で、「本人は安心できているか」「本人の選択が尊重されているか」などのアウトカムは評価の対象とされていない。
本来、手段の1つであるべき「よりよい医療・ケア」が目的化され、その結果、本人や家族は幸せに暮らせているのか、という点が省みられることはない、というよりも、要介護・認知症で幸せに暮らすなんて無理だ、と最初からあきらめている現場もあるように思う。
自分自身も、自分たちの家族も、長生きすれば、いずれ要介護・認知症になっていく。この誰もが通る道を、安心・納得できるものにしていく。それが、いずれ当事者となる全員の責務だ。
本人と、家族と、地域(市民)と、そして専門職と。
最適な役割分担の中で、その人らしいくらしを継続していく。
それをスムースにするために必要なのは、フレキシブルな取り組みを邪魔しない制度や基準の在り方を考えること、そして私たち一人ひとりが、家族の関わりも含め、これから先の人生にきちんと向き合うことなのかもしれない。